肥満と肥満症のただしいミカタ研修
「やせられないのは努力が足りないから」、「太ってしまったのは自己管理ができないから」
―本当にそうでしょうか?
一般的に「肥満」に至った要因は生活習慣にばかりフォーカスが当てられ、「自己管理の問題」として捉えられがちです。しかし、その思い込みが「肥満症」という疾患のただしい理解や治療の妨げになっている可能性があります。
誰もがより健康で、より豊かな人生を実現できるように。
肥満や肥満症に対する無意識の誤解や偏見に気づき、その背景にある複合的な要因を知ることから、健康な職場づくりをはじめてみませんか。
肥満や肥満症を正しく知り、理解し、向き合うプロジェクト
「肥満と肥満症のただしいミカタ研修」
身近なコミュニティである「職場」から、「肥満」への誤解や偏見を解消し、「肥満症」という慢性疾患への正しい理解を社会に広めていくために
近年、企業などで健康経営やウェルビーイングに関する取り組みが広がる中、様々な疾患の上流にある「肥満症」は、肥満症のある人のQuality of Life(生活の質)の低下や、他の健康障害の発症や悪化リスクを伴うにもかかわらず、疾患として十分に認知されていません。「肥満」と混同されやすいために見過ごされがちであったり、これまで治療選択肢が限られていたことから、他の疾患と同じレベルでの適切な治療がなされてこなかった現状があります。
この課題を受け、日本イーライリリーと田辺三菱製薬は、まずは職場から「肥満症」への正しい理解を深め、肥満症のある人や周囲の人々がより健康で豊かな人生を実現できるよう、健康な職場づくりを目指す「肥満と肥満症のただしいミカタ研修」プロジェクトを発足しました。
「肥満と肥満症のただしいミカタ研修」では、本プロジェクトで開発したユニークなワークショップツールを活用し、「楽しく」、「ただしく」、肥満や肥満症に関する誤解や偏見、正しい情報について学ぶことができます。参加者への啓発や教育を通じ、健康な職場環境の構築に寄与することを目指しています。
さらに本プロジェクトでは今後、コンテンツを他の企業や団体へも広く展開し、社会における「肥満」や「肥満症」への理解の輪を広げていくことを目指しています。

肥満症とは
「肥満」はBMI25以上の状態、「肥満症」は肥満+合併症をもった慢性疾患
日本における「肥満」は、脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態で、体格指数(BMI)25以上と定義されています。一方で「肥満症」は、肥満(BMI25以上)があり、かつ肥満に起因ないし関連する健康障害(合併症)を1つ以上有するか、あるいは内臓脂肪蓄積がある場合など関連健康障害の合併が予測され、医学的に減量を必要とする病態と定義されており、減量による医学的治療の対象になる慢性疾患です*1。
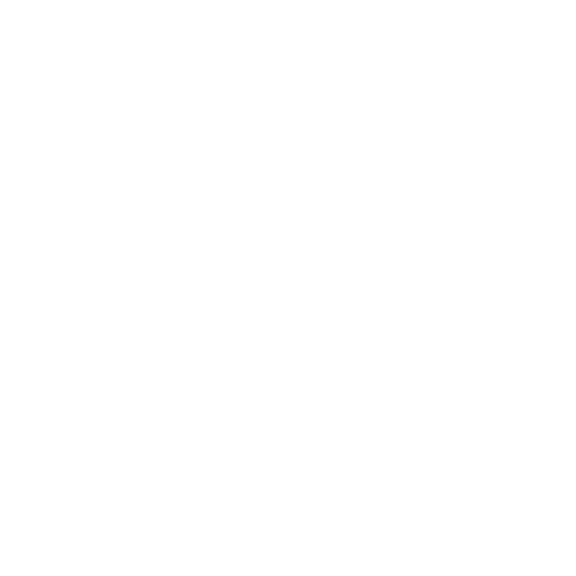
肥満と肥満症とメタボのちがい*2

日本には「肥満」に該当する人口が2,800万人*3 いるとされていますが、そのうち肥満に関連する健康障害を合併する「肥満症」の診断や治療は、これまで治療選択肢が少なかったこともあり、他の慢性疾患に比べて積極的に行われてこなかった状況があります。
肥満や肥満症の発症には、個人の生活習慣のみならず、遺伝や環境、身体的、心理的、また社会的などの要因が複合的に組み合わさって関与しており、本人の努力だけでは解決が難しいと言われています*4。それにもかかわらず、「肥満は自己管理の問題」という誤解や偏見(オベシティ・スティグマ)が社会課題として存在しており、本人の努力や生活習慣のみがフォーカスされがちです。
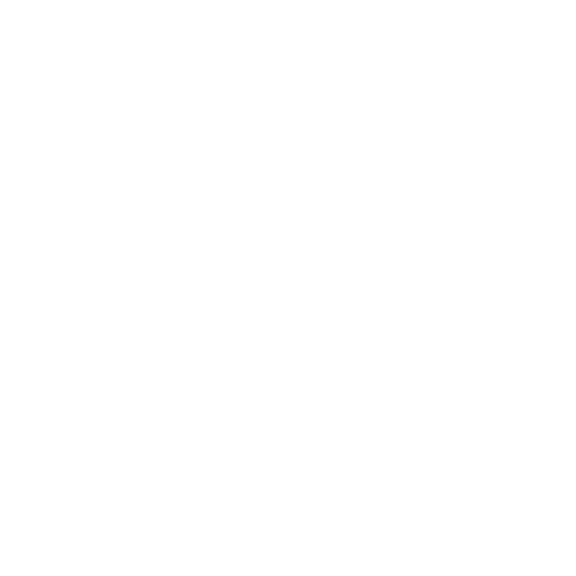
肥満症の要因*4

|
環境・生活習慣因子 |
:
食生活、身体活動、低栄養・高エネルギー・超加工食品の普及など |
|
遺伝子因子 |
:
肥満の要因の40~70%は遺伝によるものと考えられています |
|
ホルモンバランスの乱れ |
:
ホルモンバランスの乱れは食物摂取及びエネルギー消費に影響します |
|
睡眠不足と概日リズム障害 |
:
睡眠不足は、ホルモンバランスの乱れにつながる可能性があります |
|
心理的因子 |
:
ストレス、不安、うつ病などの心理的問題は、肥満と密接に関連します |
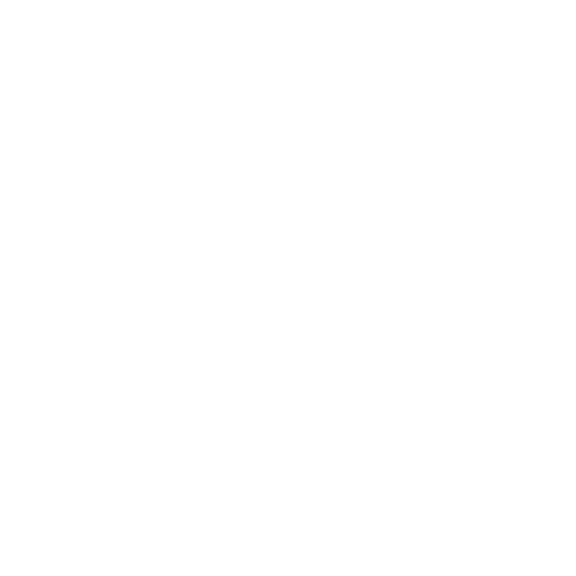
「肥満と肥満症のただしいミカタ研修」活動紹介
◆「楽しく」学べるワークショップと「ただしく」学べる疾患解説によるプログラム
両社は2025年3月4日の「世界肥満デー」に合わせ、初回の研修を実施。社員同士が日頃身近にある肥満に対する誤解について、カードゲームを通して楽しみながら気づき、知り、理解を深めました。
前半のワークショップでは、参加者4~5人のグループに分かれ、「偏見カード」を使ったカードゲームを楽しみながら、提示された身近な「あるある」なシチュエーションと、そこに潜む肥満に対する偏見に気付き、知りました。さらに、参加者同士で意見を共有しながら、肥満や肥満症の複合的な要因について学びを深めていきました。
後半のセッションでは、本プロジェクトの医学監修者であり肥満症の専門医である小川 渉先生(神戸大学大学院医学研究科 橋渡し科学分野 代謝疾患部門 特命教授)を講師に迎え、「肥満症」についての専門的な解説を通じて、疾患にに対する理解をより深めるとともに、「ただしく」学ぶ機会となりました。
本コンテンツは今後、他の企業や団体へも広く提供し、社会における「肥満」や「肥満症」に対する理解の輪を広げていくことを目指していきます。

◆ワークショップツール「みえない偏見カード」
日常に潜む「肥満の要因」に対する誤解や偏見に気づく、対話型カードゲーム
「みえない偏見カード」は、日常に隠れる「肥満は自己管理の問題」という、肥満の要因に対する誤解や偏見に気づくための対話型カードゲームです。身近な「あるある」なシチュエーションを題材に、普段は気づきにくい偏見の存在を可視化し、参加者同士で意見を交わしながら理解を深めます。
医師監修のもと開発されたこのツールは、楽しく学びながら「肥満」や「肥満症」という疾患を正しく理解する第一歩となります。

肥満症のある方の声(約7分)
「あなただけのせいじゃないよ」って、今なら言ってあげたい。
肥満症専門医からみた本プロジェクトの意義
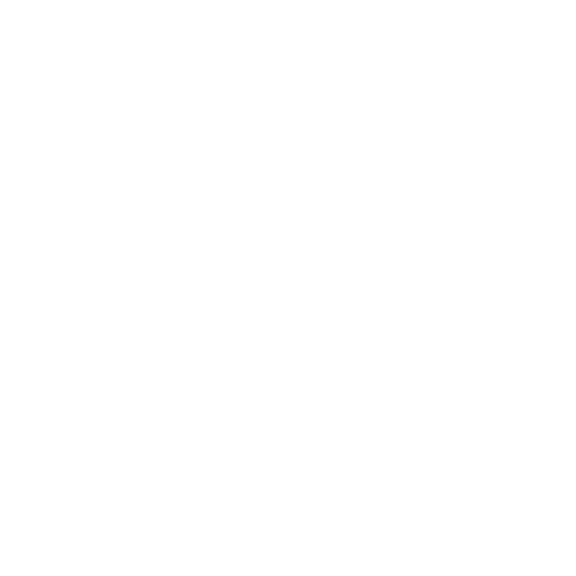

【監修医師】
小川 渉 先生
神戸大学大学院医学研究科 橋渡し科学分野 代謝疾患部門 特命教授
肥満症は、QOL(生活の質)の低下だけでなく、他の健康障害を引き起こすリスクや、既に患っている他の疾患を悪化させるリスクがある、公的な健康保険で治療することが可能な慢性疾患です。様々な要因が重なって発症するため、決して自分自身の生活習慣の問題だけに依存するものではありません。しかし、「肥満は自己責任」という肥満症当事者も含めた社会の誤解や偏見、いわゆる「オベシティ・スティグマ」が、病気であるという理解や必要な治療の妨げとなっています。肥満症への正しい理解を促進するためには、社会全体が肥満に対する誤った見方を変えていく必要があります。『肥満と肥満症のただしいミカタ研修』を通して、医療現場だけでは解決しきれない肥満症への理解の輪が、職場、そして社会に広がるきっかけとなれば嬉しく思います。*1:日本肥満学会「肥満症診療ガイドライン2022」, p.1-2
https://www.jasso.or.jp/data/magazine/pdf/medicareguide2022_05.pdf
*2:日本肥満学会. あなたの肥満、治療が必要な「肥満症」かも!?: https://www.jasso.or.jp/contents/wod/index.html(2025年4月閲覧)
*3:厚生労働省 国民健康・栄養調査(令和元年): https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000687163.pdf(2025年4月閲覧)
*4:Schwartz MW, Seeley RJ, Zeltser LM, et al. Obesity Pathogenesis: an Endocrine Society Scientific Statement. Endocr Rev. 2017;38(4):267-296.
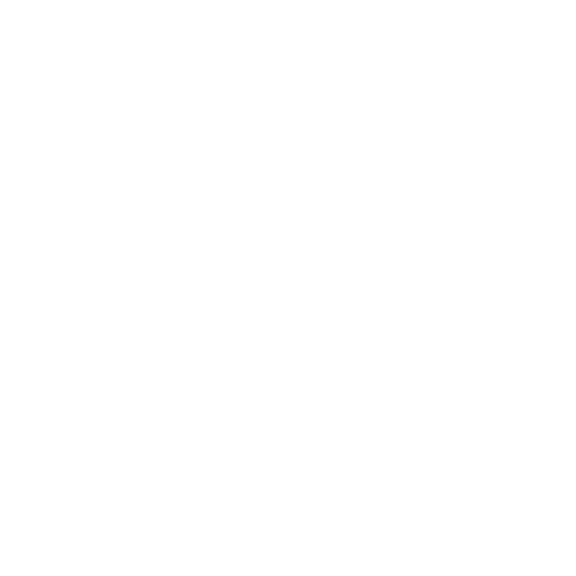
 日本イーライリリー株式会社
日本イーライリリー株式会社
 田辺三菱製薬株式会社
田辺三菱製薬株式会社